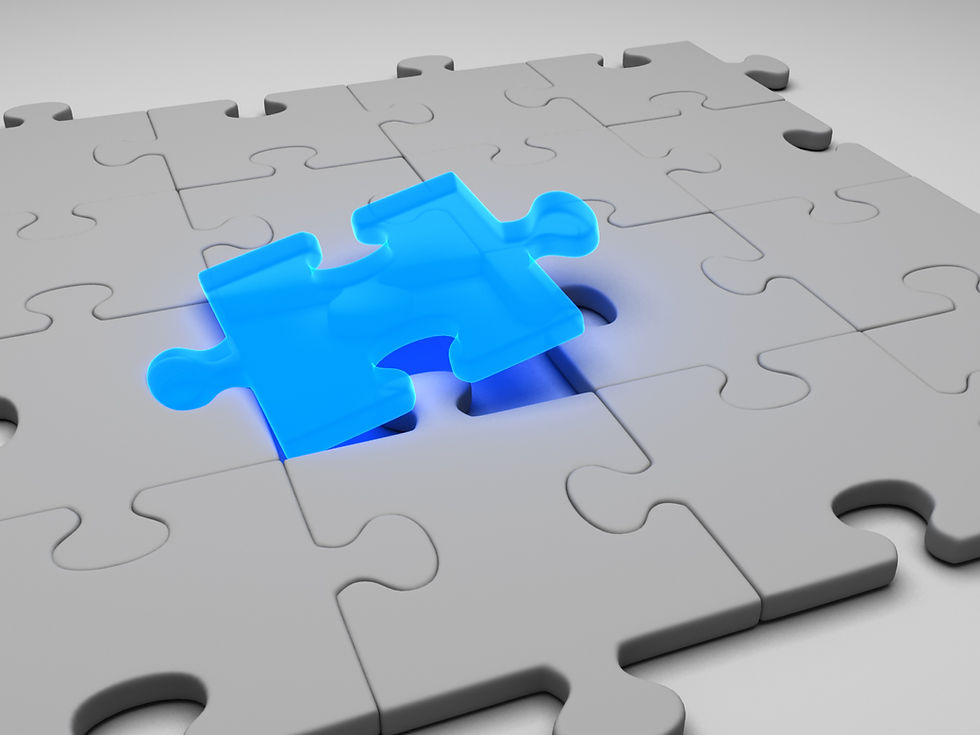法律だけでは防げない現代のトラブル──全体像を見通す力の必要性
- secinnovpjt
- 2025年3月16日
- 読了時間: 4分
先日、ある配信者に関する痛ましい事件が報じられました。
金銭のやりとり、民事訴訟、そして最終的には深刻な事態へ。
その一連の経緯に、多くの人が「なぜ防げなかったのか」「法律で解決できなかったのか」と感じたかもしれません。
こうした問いかけは、決して他人事ではありません。
むしろ現代社会において、どこにでも起こり得る問題であり、私たちは今一度、「トラブルへの向き合い方」そのものを見直す必要があるかと思います。
なお、事件当時者の倫理的な背景については様々な意見があるかと思いますが、ここではあくまで「事象の構造を分析すること」についてのみ焦点を当てたいと思います。

■ 現代のトラブルは、法律の枠に収まらない
トラブルと聞くと、まず思い浮かぶのは「法律問題」です。
たしかに、契約不履行や債権回収、損害賠償といった法的論点は、重要な解決手段です。
しかし、現実のトラブルの多くは、法的な構成要件だけでは説明がつかない複雑さを内包しています。
たとえば、
心理的な執着や依存関係
デジタル上での関係性の曖昧さと誤認
経済的な貸与や援助と感情的なすれ違い
社会的孤立や生活背景による判断能力の揺らぎ
安全確保やリスク感知の制度的限界
これらが折り重なることで、問題は単なる「法律問題」から、多層的・動態的な“リスク構造”へと変貌していきます。
■ 自力救済が生む“法律の無力地帯”
こうした構造の中で、特に見落とされがちなのが、「自力救済」という行動の危険性です。
たとえば、法律に基づいて手続きを進めたにもかかわらず、金銭が返ってこない。
その結果、「自分の手で取り戻すしかない」と考えてしまう──。
これは、決して稀なことではありません。
しかしここで、あらためて考えるべきなのは、法律は“自力救済を選ぶ心理”そのものを止める力を持たないという事実です。
法律は制度であり、行動に先んじて働きかけるものではありません。
つまり、「裁判を起こしたけれどダメだったから直接交渉に行く」「SNSで相手を攻撃する」「怒りの矛先を感情で処理する」といった展開は、法律の守備範囲を超えてしまいます。
これは、法律の不備ではなく、社会的支援構造の空白地帯だと捉えるべきでしょう。
■ 「顧問弁護士がいれば安心」という落とし穴
実は、こうしたリスクは一般の企業や団体でも十分に起こり得るものです。
たとえば、芸能事務所、病院、女性の多い職場など、従業員が仕事上でトラブルに巻き込まれやすい業種では、
「うちは顧問弁護士がいるから大丈夫」
と考えてしまう経営者は少なくありません。
もちろん、法律の専門家がいること自体は重要です。
しかし、顧問弁護士が対応できるのは、基本的には「法律で取り扱える領域」に限られています。
ところが実際には──
トラブルの背景にある心理的要素
職場環境や安全体制の整備
社内報告ルートの不備や対応方針の不明確さ
周囲との関係構築・職員教育の不足
といった“非法律領域”こそが、トラブルの根源になっているケースも多いのです。
法律対応“だけ”では、実は十分とは言えないケースが増えています。
■ 問題は“全体構造をどう見通すか”にある
私たちが本当に必要としているのは、
「法律か、心理か、教育か」という個別論ではありません。
必要なのは、それらを一つの構造として読み解き、どの段階で何に手を打つべきかを整理できる視点です。
ところが、現実にはこのような視点を持って支援できる人材は、極めて限られています。
そして皮肉なことに、もっともトラブルに関与しやすい職業──弁護士やカウンセラー、管理職──であっても、トラブルが持つ複雑性に対して、“構造的理解と対応設計”まで視野に入れている人はほとんどいません。
■ 必要なのは、“統合的支援の設計者”
現代社会に求められるのは、「対処」ではなく「構造設計」です。
つまり、可能であればトラブルが起こる前から予兆を可視化し、起きたときには全体フローで対応し、再発を防ぐ仕組みを組み立てる視点です。
リスクの見える化
自力救済を防ぐ初期対応設計
法律・心理・安全の連携導線
組織対応フレームと職員教育の内在化
こうした“横断的・総合的支援の設計者”が、これからの社会には不可欠です。
■ 最後に
トラブルに遭遇したとき、私たちはつい、「誰が悪いのか」に目を向けがちです。
しかし、本当に大切なのは、「なぜ問題が深刻化するのか」「どうすれば未然に止められるのか」です。
法律は必要ですが、十分ではありません。
そして、問題の構造を俯瞰し、多層的に支援できる存在こそが、今の社会に最も不足しているものです。
私たちは、そうした支援設計を行うコンサルティングを通じて、個人や組織がより安全かつ健全に機能できるよう支援しています。
“対処”ではなく、“設計”。
その視点の重要性を、あらためて広く伝えていきたいと考えています。